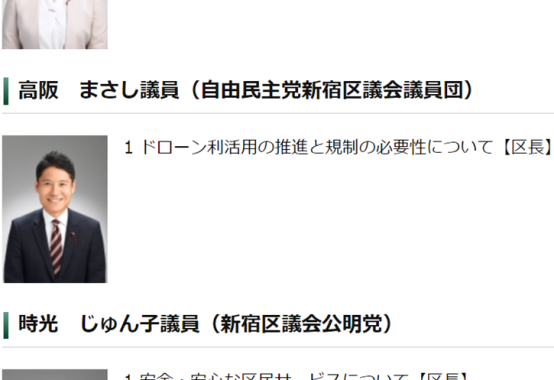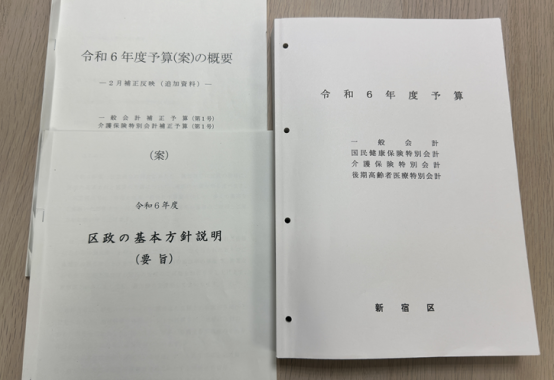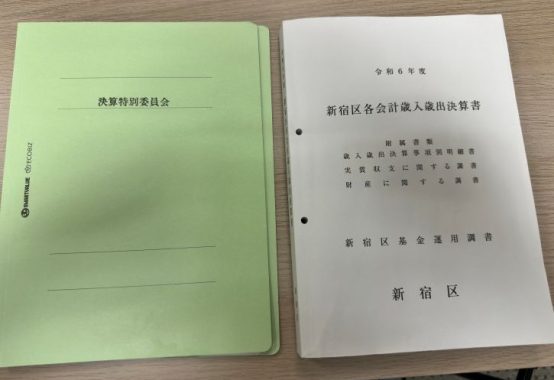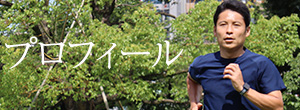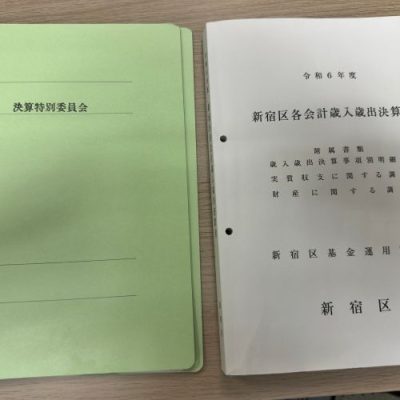新宿区議会では2/19(水)~3/24(月)までの34日間、第1回定例会が開かれました。
今定例会では来年度の予算案を審議する「予算特別委員会」も設置され、各会派から委員が出席して役所側と激しい(?)質疑が繰り広げられました。※私は今回、予算委員ではありませんでした。
予算特別委員会に先だつ2/26(水)の本会議で、私は会派の代表質問に立ちました。
1.令和7年度予算について
2.今後の区財政運営について
3.激動する社会を生き抜く子どもたちへの教育について
4.区立公園の活用について
5.区民からの声に対する区の姿勢について
※質問の様子は区議会ホームページで動画が公開されています。
代表質問は「会派を代表して」行う質問ですので、すべての質問が私の考えだけを反映させた内容というわけではありません。今回の質問で言うと「4.区立公園の活用について」と「5.区民からの声に対する区の姿勢について」が、自分だけで作り上げた質問になります。
「4.区立公園の活用について」は、「犬の散歩の際に公園に入れるようにしてほしい」という、普段の議員活動の中でもよくいただくご意見をもとに作りました。
現状では、区が独自に設けた要件をクリアできる一部の公園では犬を連れて入ることが認められていますが、ほとんどの公園では「禁止」となっています。
もちろん、公園を利用する人の中には犬が苦手な方や小さな子どももいますし、騒音の心配もありますので、配慮が必要なことは間違いありませんが、例えば「早朝や深夜の時間帯に限定」、「地域の方に定期的な清掃や(静かに利用するなど)管理の協力をしていただく」といった工夫で、犬を飼っている方、犬が苦手・嫌いな方など、多くの人が受け入れられる内容にすることは十分可能だと私は考えています。
白銀町にある白銀公園では上記のような取組みを条件に、犬が入れる時間帯を設ける実証実験が平成17年より行われており、一定の成果も出ています。ここで得られた知見をもとに、他の公園でも地域ニーズに応じて実証実験の対象を広げてはどうかを問いました。
「5.区民からの声に対する区の姿勢について」は、↑↑犬を連れての公園利用とも関係していますが、意見の対立する政治課題に対する区としての施策や意思決定の中に、一方の主張する利益が結果的に不均衡に反映されてしまっているものも一部あるのでは?という問題意識のもと、功利主義や公正としての正義(ジョン・ロールズ)といった政治哲学にも触れながら、区の認識や今後の方針を問うたものです。
近頃、自分の権利や利益は強く主張する一方、他者の権利や利益は軽視するような風潮も社会の一部で漂っています。例えば「騒がしいから」という一方的な理由で、「公園で子どもを遊ばせるな、ボール遊びをさせるな」「体育館の窓を開けて授業をするな」「幼稚園や保育園の園庭で園児を静かに遊ばせろ」「盆踊りをするな」「除夜の鐘をつくな」という声まで挙がる例も耳にします。
「政治とは意見の異なる複数のアクター間における利害調整の場である」というのは、これまで多くの政治学者によって定義づけられてきた「政治の役割」の1つですが、そうした利害調整に際しては、意思決定プロセスの公正性やアクター間の利益配分の公平性にも十分配慮しなければなりません。
「犬連れで入れる公園を認めるのに非常に高度な要件を設ける」「公園でのボール遊びは原則禁止」「学校施設開放事業で、ボールのはずむ音がうるさいという理由でバスケットボールができない体育館がある」--これらは区役所に実際に届いた声を反映し、区が講じた施策の一例です。
しかしこうした施策では、「周辺住民の住環境の保持」という利益はある程度実現される一方で、犬連れの方、子どもたち、バスケットボールをしたい区民に対してはアンバランスな制約が課されています。声を挙げる者が主張する権利や利益が相対的に不均衡に保護され、言わば「言った者勝ち」のような様相を呈しており、決して公平な利益配分になっていない、と私は考えています。
区議会議員に当選してからのこの2年間、区の施策の中でこうしたものがたまにあるなと感じており、何らかの改善が必要だと考えています。
…などと自分なりに理論立てて丁寧に質問したつもりですが、役所からは「つれない答弁」をいただいてしまいました。新宿区議会では、私の所属する自民党はいわゆる「与党系」に分類されますが、与党系会派の代表質問としては「0点」に近い答弁をもらうことになりました。
質問スタイルはそれこそ議員それぞれ十人十色ですが、役所から良い答弁をもらえるよう事前に綿密に打ち合せした上で質問を作ることも珍しくない中、私はどちらかと言うと自分の主張や考えをもとに、言いたいことを言うスタイルを採っています。
質問の仕方に柔軟性を持たせて「実」をとれるようになることも自分自身の課題だな、と認識させられる代表質問でした。