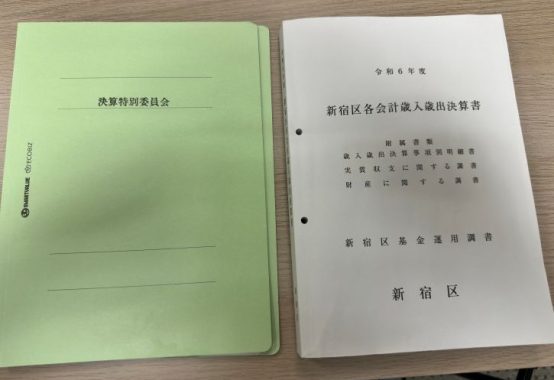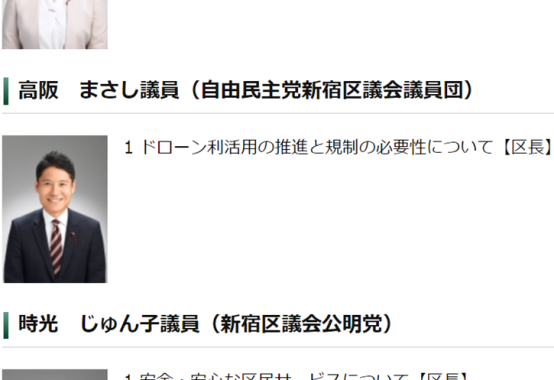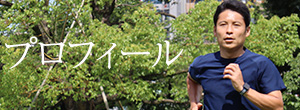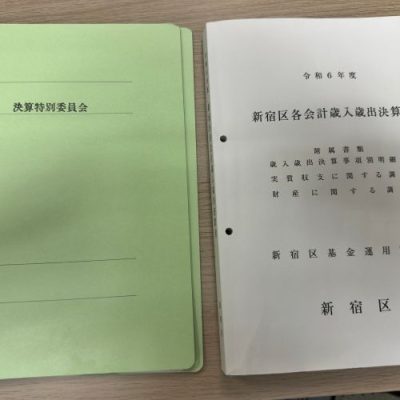9/24から10/20までの27日間、新宿区議会では第3回定例会が開かれました。
9/25の本会議では「損害賠償責任の一部免責に関する条例」について、一般質問に立ちました。
※質問の様子は区議会ホームページで動画が公開されています。
今回の質問も、地域の方からお伺いしたお声の1つがきっかけです。
少し前に地元を歩いていると、「区長が巨額の損害賠償を求めて訴えられているらしいけど大丈夫なの?」と区民の方から連日尋ねられる、という珍しい(?)経験をしました。
とある開発計画に反対する方々が、吉住健一区長個人に対して10億円(!)以上の損害賠償を行うことを区に求めて提訴しており、そのことを発信した区長のSNSをご覧になった方が心配して私に声を掛けてこられた、というものです。
その訴訟のことはさておき……
首長(知事・市長・区長・町長・村長)や役所の職員に対して、損害賠償を請求するよう地方自治体に求める住民訴訟(いわゆる4号訴訟)は、全国いたるところで起きています。
一昔前には、官官接待やカラ出張など、役所内部での不適切な行為・慣習も珍しくはなかったようですし、また地方議員の政務活動費の使い方も、今とは比べものにならない“ザル”だったということも先輩議員からは聞きます。
住民訴訟はこうした行為や慣習を正すために、これまで非常に大きな役割を果たしてきました。
その一方で、首長や役所の職員が適切に業務を行っているのに、何らかの施策に反対意見を持つ人が、嫌がらせのように巨額の損害賠償を求めるよう提訴する住民訴訟(4号訴訟)も、残念ながら存在します。
こうした事態についてはかつて「首長や職員が萎縮してしまう」「創意工夫を凝らした施策に挑戦できない」といった課題が指摘され、平成29年の地方自治法改正へとつながりました。
この法改正の中では、“善意かつ重大な過失がない場合”は、たとえ首長や職員に損害賠償の責任があるとしても、その金額があまりに高額にならないよう条例で定められるようになりました。
今や全国の地方自治体で条例の制定が進み、区の答弁では約450区市町村で制定済みの中、新宿区ではいまだに条例が制定されていませんし、その動きも見られません。
役所の仕事は年々、増大化・複雑化・高度化しています。次々に新しい課題が発生し、それに対応するために新しい業務が生まれ続けています。また、法律や条例もどんどんと制定・改正され、それに伴って首長や職員に求められる能力も増えていく一方です。
両肩にかかるプレッシャーが日に日に大きくなっていく状況の中で、訴訟による損害賠償を過度に恐れて、挑戦的な施策に取り組めなかったり、声の大きな少数意見に過度に配慮した施策が講じられたり、といったことが頻繁に起こってしまえば、役所の仕事の質は低下し、目に見えない損害を区民がこうむり続けるような事態につながります。
条例制定がそうした事態を回避する最善策とまでは言いませんが、一助にはなると考え、免責条例制定に対する認識や方針を問いました。
答弁では、必要性については認識しているものの、いつまでにどうこうするといった明確な見通しはなく、慎重に検討するということでした。いつかは条例を制定することになるとは思いますが、少しでも早くなるよう、引き続き意見していこうと思います。
今回の質問の内容は「○○という支援策を講じるべきだ」「○○の制度を変えて区民の利便性を向上させてほしい」などといった質問と比べて効果が見えづらいため、「そんな条例を制定したからって何のメリットがあるんだ」と思われる方もおそらく多いと思います。
次回の質問はもう少しイメージしやすいような内容にしようかな、と考えているところです。